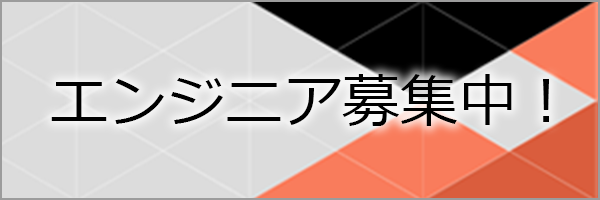目次
- はじめに
- UXデザインの実践について
- ヒューリスティック評価
- アンケート実施
- 下期の活動内容について
- その他の活動について
- さいごに
1.はじめに
皆さん、こんにちは。エクスペリエンス&ビジネスデザインセンター(通称:EBC)若手メンバーです。
私たちは、週1回の勉強会の中で、日々の業務や学習で得た知識・スキルの共有や、テーマを決めてUXデザインの実践を行い、UXデザインスキルを磨くことを目的として活動しています。今回は、UXデザインの実践として具体的に取り組んでいることを皆さんにお話しします。
- エクスペリエンスのデザインって何をやっている部署?
- UXデザインの実践ってどうやるの?
などに興味のある方の参考となれば幸いです。
サービスデザイン支援ワークショップ|株式会社クレスコ (cresco.co.jp)
2.UXデザインの実践について
私たちは昨年度、社内の交通費精算システムを題材にUXデザインの実践、UI改善を実施しました。
UXデザインの実践ってどうやるの?クレスコの若手勉強会について | Tech Blog | CRESCO Tech Blog
より実践的な取り組みであったことから、学習した内容を普段の業務にそのまま活かすことができるとメンバー全員が感じました。そこで、本年度も実在するアプリを題材にUXデザインに取り組みたいという熱意が高まり、身近なヘルスケアアプリの改善を課題と設定しました。また前回に引き続き、当社社員が「ユーザー」でもあり、使いづらいと感じたことがあることから、UXデザインのプロセスを一から実践するのに適していると考えた理由の一つです。
改善案の検討にあたり、以下のプロセスで進めてきました。
- ヒューリスティック評価(チェックリストに基づく評価)
- ユーザー調査(利用者の視点での使用感の調査)
現在はUX設計に取り組んでいる途中ですが、それぞれどのようなことを行ったのか(行うのか)をご紹介します。
3.ヒューリスティック評価
皆さん、こんにちは。EBCの納谷と野口です。
私たちからは、ヒューリスティック評価についてお話します。
ヒューリスティック評価とは、システムやサービスのユーザビリティをチェックリストによって評価することで、UI上の問題を発見する方法です。
今回はヒューリスティック評価として、以下の2つを行いました。
- ヘルスケアアプリの改善が必要な箇所と重要度の整理
- 改善が必要な箇所もとにユーザビリティを点数で評価
1. ヘルスケアアプリの改善が必要な箇所と重要度の整理
各メンバーが気になった点と、どのように改善すれば良いのかをそれぞれ書き出しました。その後、書き出した内容をもとに、ウォークスルー形式で指摘を一つ一つ全員で協議しながら、改善が必要な優先度を1~3段階でつけていきました。
2. 改善が必要な箇所及び改善方針の整理
チェックリストは、
- ブラウザやOSの機能を制限していない
- ヘルプやマニュアルが用意されている
といったような評価項目で構成され、達成の度合いをつけていくものです。
チェックリストもとにメンバー全員で評価を行いました。
また、昨年度評価した交通費精算システムは基本的に、デスクトップ向けのWebサービスでしたが、今回はモバイルアプリだったため、スマホ特有の観点も評価する必要がありました。
例を挙げると、
- タップできるような見た目になっているか
- 1画面内の情報が多すぎないかどうか
などの観点で評価しました。
ヒューリスティック評価の結果として挙げた指摘は大きく3つに分類できました。
- 操作(タップ)できる部分が分かりづらい
- 機能の説明やガイドが足りない
- 文言の表現がそろっていない
1と2の指摘はユーザーの操作に直接関係する部分であり、使いづらさを引き起こしやすい問題です。そのため優先度を高く設定し、なるべく早く改善を行えるよう計画をする必要があります。
今回の若手勉強会での活動では昨年度と異なりヒューリスティック評価の対象を一つの機能に絞らず、モバイルアプリ全体にしたため評価はもちろんのこと、評価後のウォークスルーを行うのに範囲が広くとても苦戦しました。また題材としたモバイルアプリ自体を利用した経験も少なく、実際に操作し挙動を繰り返し確認しながら行う形であったため、より業務に近い形で実施できた点は非常に良かったです。
4.アンケート実施
皆さん、こんにちは。EBCの中里です。
ここからは、アンケート実施についてお話しします。
まず、私たちはアンケート実施に向けて、すぐ計画に着手したわけではありませんでした。
本来の計画では、アプリ利用時の基本導線やユーザーのインサイトを探ることを目的に、ユーザーインタビューを行う予定でした。
この計画を変更することとなった経緯も含めてご説明します。
ヒューリスティック診断を終えた私たちは早速ユーザーインタビューに向けて計画を立て始めましたが、ここで1つ問題が出てきました。
それは、ヘルスケアアプリの利用目的が限られすぎていて、メインのユースケース(ユーザーが利用する際に最もベーシックとなる利用手順)が想定できなかったことです。
メインのユースケースに沿ってインタビュイーにヘルスケアアプリを操作してもらい、行動観察を通してインサイトを探り、事前のヒューリスティック評価との比較を行う予定でした。
しかし、ユースケースが想定できないとなるとインタビュイーの時間を無駄に浪費させてしまうし、そもそもユーザーインタビューの目的を達成できないだろうという結論に至りました。
そこで私たちは、ユーザーがこのアプリをどのように利用しているのかを分析する必要があると考え、大人数を対象に展開可能で、オンラインかつ時間指定の必要がないアンケートを実施することにしました。
アプリの利用状況を分析するために、アンケートには以下の項目を用意しました。
- アプリをどのくらいの頻度で利用しますか
毎日 週に数回 月に数回 ほとんど利用しない
(1で毎日/週に数回/月に数回利用すると回答した方) - このアプリをダウンロードしたきっかけは何ですか?
- このアプリを主にどのタイミングで利用しますか?
- このアプリを主にどのような目的で利用していますか?(複数選択可)
- このアプリに関する全体的な満足度を教えてください。
(1でほとんど利用しないと回答した方) - このアプリをダウンロードしたきっかけは何ですか?
- このアプリを主にどのような目的で利用していますか?(複数選択可)
- なぜほとんど利用しませんか? (複数選択可)
アンケートを部内で実施した結果、利用頻度の項目において、利用しないと回答したのは12名中10名いました。
また、利用していると答えた2名の、アプリに対する満足度は平均かそれ以下でした。
利用していないと答えた12名の方は、イベントや合宿などの催し事でアプリが必要になった際にインストールしたと答えた方が大部分で、自主的にインストールを決めた方は限りなく低いことが分かりました。
そして利用しない理由にあげているものとして一番多かったものが、その他の回答も含めると、「代替可能なアプリが存在する」「このアプリでなくてもよい」という回答でした。
このような結果を受けて、我々は本来計画していた「UI/UX改善」を活動の軸とするか、「サービスデザインの改善」を軸とするか、再度検討する必要があるという結論に至りました。
5.今後の活動内容について
皆さん、こんにちは。EBCの川辺です。
ここからは、下期の活動予定についてお話しします。
この勉強会の主な目的は、普段の業務で必要なスキルを身につけることです。
メンバー全員が業務でUXデザインを行っているため、今年度はUXデザインを行うことを計画していました。
しかし、部内で実施したアンケートの結果を受けて、ヘルスケアアプリのUXデザインを引き続き行うべきかメンバーと議論しました。
議論の結果、下期はUXデザインではなく、サービスデザインを行うことに決めました。具体的なスケジュールは改めて計画しますが、このアプリのユーザーを増やす方法を検討していく予定です。
6.その他の活動について
UXデザイン以外に行った活動をご紹介します。
若手勉強会は、基本的にオンラインで開催していますが、8月29日に皆で集まりオフラインで開催しました。
この日は、
- スマートフォンに保存している写真紹介
- バリューズカード
の2つを行いました。
写真紹介では、各自のスマートフォンに保存している写真の中で、
- 最も若い自分が写っている画像
- 今年撮影した画像の中でお気に入りの場所
の2つを紹介し合いました。
誰が最も若い写真を保存しているか勝負をしたり、知らなかった場所を知ることができたりと、楽しむことができました。
バリューズカードは、最初5枚の手札が配られます。自分の番がくると手札を1枚捨て、山札もしくは他の参加者の捨て札から1枚引きます。山札がなくなるまで繰り返し、自分の価値観に合ったカードを5枚手札に残します。最後に、手元に残ったカードを使って、他の参加者に自分の価値観を説明するというゲームです。
このゲームを通して、メンバーの新たな一面を知ることができました。
普段オンラインでしか話す機会がないため、対面で話すことができ若手メンバー間の仲が深まったと思います。下期もオフラインでの活動を予定しているので、今から楽しみです。
7. さいごに
上期ではヒューリスティック評価とアンケートの実施(ユーザー調査)を行いましたが、昨年の勉強会での経験を活かして作業をすることができ、スキルが着実に身についていると実感できました。
当初の予定から大幅に変更になりましたが、下期も引き続き頑張っていこうと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。下期の活動についてもまた Tech Blogでお伝えしたいと考えています。では、また次回のTech Blogでお会いしましょう。