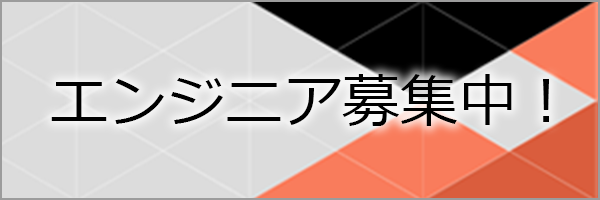この記事は「CRESCO Advent Calendar 2020」24日目の記事です。
こんにちは!エクスペリエンスデザインセンター所属のカツメです。最近はデザイン思考の実践として、サービスデザイン支援ワークショップのファシリテーターとしても活動しております。
ワークショップではペルソナ分析やカスタマージャーニーマップであったり、ユーザーの体験価値を探ったりと様々なアプローチでゴールに向かっていきます。
今回は、その中でもデザイン思考のプロセス「アイデア(Ideate)」について少し書いてみたいと思います。

「アイデア」ときいて「自分にはアイデア出しはちょっと無理だな。」なんて思いましたか?
アイデア発想は一部の人だけに与えられた才能ではなくて、誰にでもできるものなんです。
良いものを生み出すためには他のスキル同様に「慣れ」が必要だったり「コツを掴む」ことも重要ですが、アイデア出しが楽になる「発想法」というものがあるんです。
いきなり「新規事業のアイデアをどうぞ!」と言われてもパッと思いつくものではないので、弊社ワークショップ内では「発想法」を用いることでアイデアが出しやすい状態を作っていきます。
今回はその「アイデア発想法」についていくつかご紹介したいと思います!
目次
アイデア発想は一度発想して終わり、というイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。
アイデア発想は思考を発散していく段階と出たアイデアをまとめあげ収束させていく段階とがあり、発散と収束を繰り返していくことでより質の高いアイデアになっていきます。
つまり、いきなり素晴らしすぎるアイデアが出るなんてことは稀の稀です。
たくさんのアイデアを出していくと、それまでに出たアイデアに触発されて新しいアイデアが出てきたり、アイデア同士を組み合わせて新しいアイデアが生まれたりします。
ですので、まずは質より量を重視して発想していきます。
発想の技法としてまず、発散する段階の技法、収束する段階の技法、発散と収束両方に対しての統合技法という分類があります。
発散する段階の技法の中には自由に発想する自由発想法と、いくつかの情報を提示して発想する強制発想法、アナロジーからヒントを得る類比発想法とあります。
(自由連想法と「発想」が「連想」となって言われることもあるようです)
自由発想法には皆様よく知る「ブレスト(ブレインストーミング)」があります。会議で自由に発言してアイデアを出していく方法です。
強制発想法では、ブレインストーミングを考案したアレックス・F・オズボーンが作成した「オズボーンのチェックリスト」が有名です。チェックリストにあるワードを対象に掛け合わせてアイデア発想していく方法です。
類比発想法には「NM法」というキーワードから類比を連想し、類比の背景を探りアイデアを発想していく方法があります。
また、「発想法入門(著:星野 匠)」では以下の4つのタイプで分類しています。
- 分析した情報から発想する方法
現在あるものやこれから作るものに対して分析し、その情報をもとにアイデア発想をしていく方法。 - 連想や刺激から発想する方法
写真や映像、言葉などを刺激材料としてアイデアを発想していく方法。 - 図に描いて発想する方法
視覚的に刺激する方法。描くことによって全体像を把握しやすくなります。 - 発想を転換させる方法
見方を思い切った発想の転換や、新しい着想を得るための方法。
少し平易になってイメージしやすい分類になっていますね。いろいろ分け方がありますが、次の章から上記分類ごとに発想法をピックアップして紹介したいと思います。
現在あるものの欠点を挙げ、その対処方法を考える問題解決型のアプローチです。
現在あるものからスタートするので、現実的で具体的なアイデアがでやすい発想法です。
発想は1人でもできますが、人によって気づく点が違うため5〜6人は参加した方がよいでしょう。
- テーマ(課題)を出す
「○○に対する不満」など欠点を挙げられる課題にします。
この時、誰の不満なのかターゲットを設定しておくと、より具体的な欠点が挙げることができます。 - 参加者に欠点を挙げてもらう
欠点はどんな些細なことでもよいですし、様々な角度から自由に挙げた方がよいので他人の意見を批判したりしないのが望ましいです。 - ピックアップ
挙げられた欠点の中から、これはというものをピックアップします。 - アイデア発想
欠点を補うもの、欠点を改善するものについてアイデアを発想します。
「○○」の部分を自社のサービスに設定すると、サービスの改善案を考えられるでしょう。
現状のサービスの改善案を考えるのであればカスタマージャーニーマップを作成してもよさそうです。ユーザーのステップごとに課題を出せるため、サービスの全体像を把握しながら自社サービスの解決策を検討しやすいです。
「○○」の部分を業種全体を指すように設定すると、新製品の企画時のアイデア発想などに使えそうです。欠点の対処法を考える発想法なので、その他組織開発やリクスマネジメントにも使えます。
刺激を受けそうな言葉を書いたカードを作ります。カードをかき混ぜてから引き、出てきたカードから連想して発想する方法です。刺激語カードで強制的に範囲を狭めてアイデアを引き出す方法になります。
特定の製品に対してのアイデアを得る場合は「別な言葉で定義しなさい」や「もし形を変えたらどうなる?」などののような指示や質問を書きます。
新製品の企画などを行う場合はカードに単語を書いて準備したあと、2枚ひいて単語を組み合わせて発想をします。業界や発想したいテーマによって単語は変わりますが、数百語は準備しておくとよいです。
その他、ネーミングやキャッチコピー作成にも活用できます。
弊社のワークショップでは刺激語法をアレンジしてアイデア発想ワークをすることがあります。
有名なのは「マインド・マップ」。紙の中心に課題(テーマ)を書いて、それから連想されるものを放射状に書いて広げマップを作る発想法です。活用されている方は多いのではないでしょうか。
また、最近ではマンダラートも有名ですね。エクスペリエンスデザインセンターのメンバーひーが、毎日勉強する習慣をつけたい目的でマンダラートをやった記事があります。
評価基準を作って新しいポジションを発見しアイデアを練る方法です。
一番簡単なのは2つの軸を組み合わせた4つのポジションに分ける方法です。
「発想法入門(著:星野 匠)」で紹介されている例で、「スポーツドリンク」について記載がありました。
縦軸で「栄養素をアピール」と「低カロリーをアピール」、横軸で「日常的に飲む」と「スポーツの時に飲む」とすると、「スポーツドリンク」は「栄養素をアピール」で「スポーツの時に飲む」のポジションになります。
「栄養素をアピール」で「日常的に飲む」ものだと「美容ドリンク」。「低カロリーをアピール」で「日常的に飲む」ものだと「ダイエットドリンク」。「低カロリーをアピール」で「スポーツの時に飲む」ものは「クエン酸ドリンク」となるのです。
ポジションを分けてみたら、今までなかった新しいポジションが見つかることがあります。新しいポジションがみつかったら、そこに当てはまる新商品を発想します。
ポイントは2つあり、見た人がわかりやすい評価軸にすることと、新しいポジションにふさわしい演出をすることです。
発想を切り替える手段をリストにしておき、それを見ながらアイデアを発想します。有名なところでは強制発想法の説明で登場した「オズボーンのチェックリスト」やそれをもっと覚えやすい形にした「SCAMPER」があります。
オズボーンのチェックリストについて簡単に紹介しつつ「エコバッグ」について発想してみます。
以下のキーワードでアイデア発想します。
- 他に使い道はないか?
そのままで新しい使い道はないか、改造してほかの使い道はないか→手持ち部分の紐を結んで、外食の時のエプロン - 応用できないか?
他にこれと似たものはないか、何かを真似できないか→空気をいれられるようにして、座布団 - 修正したら?
意味、色、動き、音、匂いなどを変えられないか→光る生地にかえてリフレクター - 拡大したら?
長く、広く、厚くできないか、頻度や時間を増やしたら
何かを加えられないか→生地を厚く体圧分散素材で犬のベッドに - 縮小したら?
短く、小さく、濃縮できないか
省略、分割できないか、何かを減らせないか→細くして一升瓶バッグ - 代用したら?
誰か、何か、代用できないか、ほかの素材、ほかの場所ではどうか→パーカーの帽子部分が取り外し可能でエコバッグになる。
なんなら帽子部分をつけたまま物を入れたっていい。 - アレンジし直したら?
要素を取り替えたらどうか、他の順序、他のパターンではどうか→片手で持つと重いから、リュックになる。エコリュックバッグ - 逆にしたら?
上下、左右をひっくり返したらどうか、順番を逆にしたらどうか→その日のファッションに合わせてリバーシブルエコバッグ。 - 組み合わせたら?
ブレンドしたらどうか、目的を組み合わせたらどうか→手持ち部分に手袋付き。カイロを差し込む場所もあってあったかい。
・・・素敵アイデアはでませんでした!!!!ごめん!!!
その他、「シックスハット法」なんていうものもあります。「シックスハット法」のやり方と、実際にやってみた内容をこちらの記事でご紹介しています。
気軽に利用できるものから準備に時間が必要なものまで様々ですが、ここでご紹介した方法以外にも発想法はたくさんあります。
1人向きか多人数向きか、現状の改善なのか事業開発向きなのかなど、状況に応じて最適な発想法をピックアップしてアイデア発想を楽にしていきましょう。
またの機会では、アイデアを収束する段階の方法やブレストの応用方法などもご紹介できたらと思います。
では!
■サービスデザイン支援ワークショップ
クレスコでは「共通認識」をしながらチームビルディング、アイディエーション、コンセプトの策定、新しい顧客体験価値の創造などの支援を行なっています。
■クレスコのサービス&ソリューション「アジャイル開発」
サービスデザインとアジャイル開発を使用し、仮説構築と仮説検証を支援することも可能です。
今回の記事は、以下の書籍やWebサイトを参考にしました。
発想法入門 星野 匠(著)